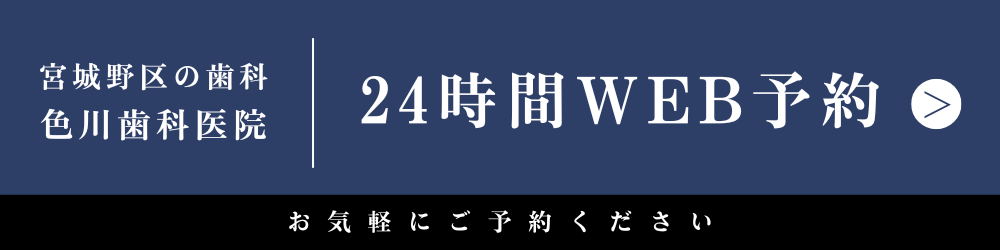2023/04/17 ブログ
口臭の対処法と予防法とは?
前回は口臭の種類と原因についてお話しました。
では、それぞれの口臭を防ぐにはどうしたらいいのか気になりますよね。
今回は対処法と予防法についてお話していきます。
対処法と予防法
唾液の減少が原因
口腔内は常に唾液による自浄作用が働いています。唾液による殺菌・抗菌作用のおかげで口の中が清潔に保たれているのです。唾液が減少すると、粘膜が剥がれたものが溜まったり、細菌繁殖を生じてしまうため、不潔な状態から口臭が発生するというわけです。
口の乾きを感じる時は、鼻呼吸を心掛け、こまめな水分補給、歯磨きやうがいをするなど出来るだけ口の潤いを保ちましょう。
また、歯を磨くのが難しい場合はうがいの他にガムを噛むことがおススメです。「咀嚼する」ことで脳に刺激が伝達され唾液分泌を促進してくれるのです。中でもキシリトール入りガムは虫歯の原因にもならないので安心して噛むことが出来ます。
虫歯や歯周病が原因
歯周病が悪化すると歯肉が腫れあがり膿んでしまうことで歯周病特有の口臭を生じます。
また虫歯にも独特の臭いがあります。しっかりと治療をすることで虫歯や歯周病の進行を防ぎ大幅に嫌な臭いを減らすことが出来ます。そして日頃の口腔ケアにも気を付けましょう。
虫歯や歯周病の原因となる歯垢(プラーク)や歯石を出来る限り減らし、お口の中を清潔に保つことが大切です。普段の歯磨きに加えてフロスや歯間ブラシ等の補助用品を使うのもおススメです。食べかすやプラークは歯と歯の間に残りやすく長時間停滞しやすいため、虫歯や歯周病、口臭の大きな原因のひとつとなります。
また義歯やブリッジといった補綴物は天然歯に比べ汚れがつきやすく、より念入りに磨く必要があります。義歯の清掃には義歯洗浄剤の併用も良いでしょう。
舌苔が原因で臭うこともあります。通常健康な舌はピンク色ですが、白い苔のようなものが舌全体に付くことがあります。これは歯垢と同じような成分で、気になるときは舌も一緒にケアしましょう。
そして硬くなった歯石はブラッシングでは取れないため専用器具で除去するしかありません。
定期的に歯科医院でクリーニングし、定期検診を受けることで清潔な口腔内を保ちたいですね。
日頃のケアに不安がある方は一緒にアドバイスを受けるのも良いでしょう。
食べ物が原因
ほとんどは時間が経てば消えるので問題ありません。一時的に臭いを弱めてくれる食品を紹介します。
・牛乳(臭いの元になるタンパク質を包んでくれる働きでニンニク等の臭いを一時的に弱めてくれます。)
・レモン、梅干し(タンパク質の分解を促進し腐敗を遅くする働きがあります。また唾液の分泌も促進されるので自浄作用が高まります。)
・お茶(葉緑素やフラボノイドといった臭い消し効果のある作用が含まれています。)
・ガム(食べかすの清掃や唾液分泌の促進に効果があります。)
口腔以外の病気が原因
扁桃腺炎、鼻炎、副鼻腔炎など耳鼻咽喉科系の疾患は、膿みが流れてきて口臭の原因になります。また喉に炎症がある場合も嫌な臭いを発します。
他には糖尿病や肝腎機能低下、悪性腫瘍などでもそれぞれ特有の口臭を呈することが知られています。
また逆流性食道炎では胃液が逆流するため胃液の臭いが臭うことがあります。
こういった全身疾患に由来するものに関しては、まずは根本的な治療が必要ですから早めに医療機関を受診しましょう。