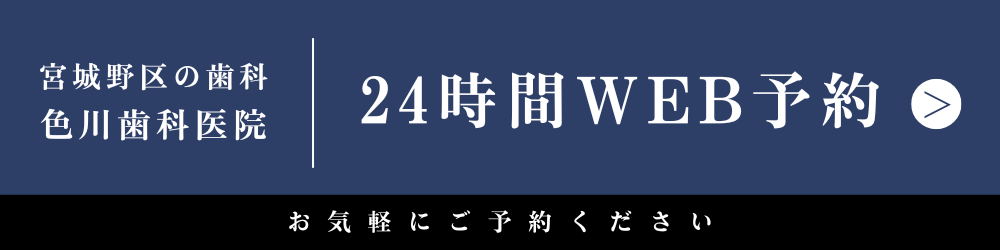2025/10/22 ブログ
マウスピース矯正中に口臭が気になるときは!原因と対策を解説
こんにちは。仙台市宮城野区「福田町駅」より徒歩4分にある歯医者「色川歯科医院」です。

マウスピース矯正は、装置が目立ちにくく取り外しができるなどの理由から、多くの人に選ばれている矯正方法です。
しかし、治療中に「口臭が気になるようになった」と感じる方も少なくありません。実は、マウスピース矯正中に起こる口臭にはいくつかの原因があり、適切な対策を取ることで十分に予防・改善が可能です。
今回は、マウスピース矯正中に口臭が発生する原因や放置するリスク、そして具体的な対処法について解説します。
目次
マウスピース矯正中に口臭が発生する原因

マウスピース矯正中に口臭が発生する原因は、以下のとおりです。
マウスピースに汚れが付着している
マウスピースは1日20〜22時間装着する必要があり、食事や歯磨きのとき以外は常に装着している状態です。しっかりと清掃しないまま再装着を繰り返すと、マウスピース表面に細菌が繁殖しやすくなります。
また、治療に使用するマウスピースは透明で、一見きれいなように見えても、実際には細菌が多く付着しています。結果的に強い口臭の発生源となってしまうのです。
しっかり歯磨きができていない
マウスピース矯正中は、食事や間食のたびにマウスピースを外し、再装着する前に歯磨きをする必要があります。
しかし、忙しい日常生活のなかで、つい歯磨きを怠ったり、簡単に済ませたりすることがあるのも事実です。そうした積み重ねが、歯の表面に食べかすやプラークを残したままマウスピースを装着する原因となり、口臭を引き起こす一因となります。
また、歯並びが少しずつ動いていく矯正中は、歯と歯の間に汚れがたまりやすくなります。そのため、矯正治療をはじめる前よりも丁寧にブラッシングを行わなければなりません。
加えて、歯間ブラシやデンタルフロスを併用しないと、歯と歯の間にたまった食べかすを完全に取り除くことは難しいのです。
歯磨きが不十分な状態でマウスピースを装着すると、密閉された空間の中で細菌が繁殖して、においが強くなります。毎食後、しっかりと歯磨きをすることが、口臭を防ぐ第一歩です。
唾液の分泌量が減少している
唾液には、口の中を清潔に保つ自浄作用があります。唾液中の成分が、口腔内の細菌の繁殖を抑え、においの元となる汚れを洗い流す役割を果たしています。
しかし、マウスピース矯正中は、装置が歯列を覆った状態になるため、唾液の自然な循環が妨げられます。その結果、口臭を発生させることがあるのです。特に水分摂取が少ない人や、口呼吸が習慣になっている人は注意が必要です。
食生活が変化した
マウスピース矯正を始めると、装着時間を確保するために食事の回数を減らしたり、間食を控えたりする人が増えます。また、マウスピースを外す手間や、歯磨きの必要性から、食事の内容が簡素になるケースも少なくありません。
これらの変化が、栄養バランスの乱れを招き、結果的に口臭を発生させることがあります。また、にんにくやネギなどのにおいが強い食品を摂取した際には、その成分が血流を通じて肺から排出され、口臭として現れることもあります。
さらに、マウスピースを装着していると、食後すぐに再装着しなければならないという意識から、十分に口の中をすすがずにマウスピースを付けてしまうこともあります。
これにより、マウスピース内で細菌が繁殖し、結果として強い口臭が発生することがあるのです、
口臭を防ぐためには、唾液の分泌を促すために食物繊維を多く含む野菜や果物を積極的に取り入れること、加工食品や糖分の多い飲料を控えることが大切です。また、食後には丁寧に歯磨きを行い、清潔な状態でマウスピースを再装着しましょう。
歯周病
歯周病は、歯ぐきの炎症や歯槽骨の破壊を引き起こす疾患で、進行すると強い口臭を伴うことがあります。マウスピース矯正中に口臭が気になる場合、歯周病が原因となっているケースも少なくありません。
矯正治療を始める前の検査で歯周病が見つかった場合には、治療を済ませてから矯正を開始するのが理想ですが、矯正中に歯ぐきの腫れや出血が見られるようであれば、注意が必要です。
歯周病が進行すると、歯ぐきから出血したり膿が出たりして、これらが口臭の原因になります。
歯周病は生活習慣病の一種ともいわれており、喫煙や糖尿病、過度なストレスとも関係しています。マウスピース矯正中は口腔内の環境が変わりやすいため、こうしたリスク要因にも気を配り、日常の生活習慣そのものを見直すことが大切です。
マウスピース矯正中の口臭を放置するリスク

口臭は単なるエチケットの問題だけではなく、健康や矯正治療にも悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、口臭を放置することで生じるリスクについて詳しく解説します。
虫歯や歯周病の進行
口臭の原因が口腔内の汚れや細菌の増殖である場合、それを放置すると虫歯や歯周病が進行するリスクが高まります。特にマウスピースは歯を全体的に覆うため、汚れが取り除かれにくく、細菌が活発に活動しやすい環境になります。
歯周病が進行すると、歯ぐきが炎症を起こし、出血や腫れを伴うようになります。また、歯周病が重度の状態にまで進行して歯がぐらつくようになると、矯正治療の継続自体が難しくなるケースもあります。
精神的なストレスや人間関係への影響
口臭に対して過敏になると、人との会話を避けるようになったり、マスクが手放せなくなったりと、精神的なストレスにつながることがあります。
特に職場や学校など、人との距離が近い環境では、自分の口臭が気になって集中力や自信を失うこともあります。また、恋人や家族とのコミュニケーションにも影響を与えることがあり、生活の質そのものに悪影響を及ぼす可能性があります。
こうしたストレスは矯正治療の継続にも関わってくるため、軽視すべきではありません。
マウスピース矯正中に口臭が気になるときの対処法

口臭は正しいケアを行うことで防ぐことが可能です。以下に、マウスピース矯正中に実践できる具体的な対策をご紹介します。
しっかり歯磨きをする
マウスピース矯正中に口臭を防ぐ基本は、やはり丁寧な歯磨きです。
矯正治療中は、食べかすや歯垢がマウスピースの中に閉じ込められやすく、口内が不衛生になりがちです。食後歯磨きをせずにマウスピースを装着すると、細菌が繁殖し、においの原因になります。そのため、毎食後には必ず歯を磨くようにしましょう。
特に歯と歯の間、歯ぐきの境目は汚れがたまりやすいため、デンタルフロスや歯間ブラシを使用して歯ブラシの毛先が届きにくい部分に付着した汚れを落とすことも大切です。
また、マウスウォッシュを取り入れることで、細菌の繁殖を抑えるだけでなく、口臭の予防にもつながります。
マウスピースのお手入れを行う
口臭の原因は、マウスピース自体の汚れにもあります。歯磨きが十分でも、マウスピースが不衛生だと細菌が繁殖し、においを発するようになります。
マウスピースは毎日水で洗うだけでなく、専用の洗浄剤を使って定期的に除菌することが重要です。熱湯を使用すると変形する可能性があるため避けましょう。
こまめに水分補給を行う
マウスピース矯正中の口臭対策として、こまめな水分補給はとても効果的です。唾液には細菌の繁殖を抑える働きがあるため、口の中が乾いた状態が続くと細菌が増えやすくなり、結果として口臭の原因になってしまいます。
特に長時間話をしているときには意識的に水を飲むことが重要です。また、就寝中は自然と唾液の分泌量が減るため、寝る前や起床後の水分補給も忘れずに行いましょう。
水分をこまめに補う習慣を身につけることで、口臭予防だけでなく体全体の健康にも良い影響をもたらします。
食生活を見直す
糖分の多い食べ物は口内の細菌のエサとなり、虫歯や歯周病のリスクを高め、それが口臭につながることもあります。
逆に、食物繊維が豊富な野菜や果物を積極的に摂ることで、口の中の汚れを自然に除去し、唾液の分泌も促進されます。さらに、栄養バランスのとれた食事は体内環境の改善にもつながり、体の内側から口臭を予防する効果もあります。
矯正中の健康的な食生活は、口臭対策だけでなく、歯と体の健康にも良い影響を与えるでしょう。
まとめ

マウスピース矯正中に口臭が気になるというのは、珍しいことではありません。
しかし、その多くは日々のケアや生活習慣によって防ぐことができるものです。マウスピースの洗浄や丁寧な歯磨き、水分補給など、基本的な対策を積み重ねることで、快適に矯正治療を進めることができます。
口臭は放置することで虫歯や歯周病といった健康上のリスクだけでなく、精神的なストレスや対人関係への影響にもつながります。治療効果を最大限に引き出すためにも、日常の小さなケアを大切にしていきましょう。
マウスピース矯正を検討されている方は、仙台市宮城野区「福田町駅」より徒歩4分にある歯医者「色川歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・根管治療や予防歯科、小児歯科、マウスピース矯正、インプラントなど、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、WEB予約・LINE予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。