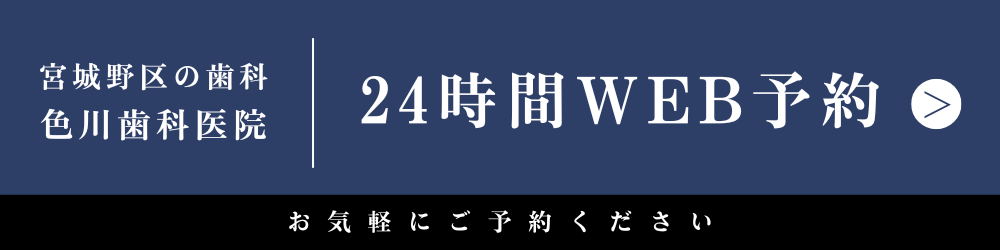2025/07/30 ブログ
親知らずが横向きに生えるとどんなリスクがある?抜き方も
こんにちは。仙台市宮城野区「福田町駅」より徒歩4分にある歯医者「色川歯科医院」です。

親知らずは、10代後半から20代前半にかけて出てくることが多いとされています。まっすぐ生えてくるとは限らず、顎のスペースが足りない場合などには横向きに生えるケースもあります。
親知らずが横向きに生えている状態は、歯並びの問題だけにとどまらず、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。例えば、隣の歯を圧迫して痛みが出たり、炎症を起こして腫れや口臭の原因になったりすることがあります。
この記事では、親知らずが横向きに生える原因からそのリスク、さらには抜歯の方法や注意点などについても解説します。
親知らずが横向きに生える原因

親知らずが横向きに生えてくる主な原因は、顎の骨のスペース不足です。硬いものをあまり噛まなくなったことで、現代人は顎が小さくなったと言われています。そのため、親知らずが生えてくるための十分なスペースが確保できず、結果として横向きに生えてくるのです。
さらに、親知らずは他の永久歯と比べて生えてくる時期が遅いため、すでに他の歯がすべて並んでいる状態でスペースに割り込むように生えてきます。これが、歯の正常な萌出を妨げ、歯が横向きに押し出されるように生えてくる理由の一つです。
また、親知らずの根が複雑な形をしていたり、骨や歯ぐきに埋もれたままになっていたりすることもあります。そのようなケースでは歯が本来の方向に進めず、結果的に横を向くこともあります。
親知らずが横向きに生えるとどんなリスクがある?

横向きに生えた親知らずは、見た目ではわかりにくいことが多いものの、口腔内にさまざまな問題を引き起こすリスクがあります。放置していると、痛みや炎症だけではなく、他の歯の健康にも悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
以下に、横向きに生えた親知らずがもたらす主なリスクを紹介します。
隣の歯を圧迫して歯並びを乱す
横向きに生えた親知らずは、隣にある第二大臼歯を圧迫することがあります。この力が継続的に加わると、歯並び全体が徐々にずれていき、噛み合わせが悪くなる原因になります。
特に、矯正治療を受けた経験のある人にとっては、せっかく整えた歯並びが崩れるリスクとなり得ます。
虫歯や歯周病の原因になる
横向きに埋まった親知らずとその周辺の歯は、非常に磨きにくいため、プラーク(歯垢)が溜まりやすくなります。その結果、親知らず自体だけでなく、隣接する第二大臼歯にも虫歯が発生しやすくなるのです。
また、歯と歯ぐきの間に汚れが入り込むことで歯周病のリスクも高まります。炎症が慢性化すると、膿がたまったり口臭が強くなったりすることもあります。
顎の痛みや腫れ・開口障害の原因になる
親知らずの周囲に炎症が起こると、顎の痛みや腫れを引き起こすことがあります。これにより、口が開けにくくなったり食事や会話に支障をきたしたりすることもあります。場合によっては、顎関節の可動域にまで影響を与え、口が開きにくくなる開口障害を引き起こすこともあります。
顎の骨や神経にも影響する
親知らずの根が顎の神経に近い位置にある場合、炎症や圧迫が神経に影響を与えることがあります。これにより、しびれや感覚の異常などが発生することがあり、症状がひどい場合には回復に時間がかかるケースもあります。
また、骨の内部で袋状の嚢胞(のうほう)ができることがあり、顎の骨を徐々に壊していくリスクも否定できません。
横向きに生えている親知らずの抜き方

横向きに生えている親知らずは、通常のまっすぐな歯に比べて抜歯の難易度が高くなります。そのため、一般歯科ではなく口腔外科での処置が推奨されることもあります。
ここでは、実際の抜歯の流れや方法について、患者さまが事前に知っておくべきポイントを紹介します。
レントゲン撮影やCTによる事前診断
抜歯前には必ずレントゲン撮影や歯科用CTスキャンを用いて、親知らずの向きや深さ、神経との位置関係などを確認します。これにより、抜歯に伴うリスクや処置の難易度を正確に把握できます。神経に近い場合は、損傷のリスクを避けるため、慎重な計画が立てられます。
局所麻酔と切開の処置
処置は通常、局所麻酔を使用して行います。麻酔が効いたことを確認したうえで、歯ぐきをメスで切開し、親知らずの位置を露出させます。歯が骨の中に深く埋まっている場合は、周囲の骨を一部削る必要があります。この工程があるため、抜歯には時間がかかることもあります。
歯を分割して取り出す
横向きの親知らずは、歯を一度に抜くのが難しいため、専用の器具を使っていくつかに分割してから取り出す方法が一般的です。こうすることで、周囲の骨や神経へのダメージを最小限に抑えられます。
分割抜歯は時間と技術を要しますが、安全性を高めるための重要な処置です。
抜歯後の縫合と止血
抜歯後は傷口にガーゼを当てて止血を行い、必要に応じて縫合します。縫合には吸収糸、または抜糸が必要な糸が使われ、使用された糸の種類によって数日後に再診が必要になります。この時点で痛み止めや抗生物質が処方されることが一般的です。
親知らずを抜歯したあとの注意点

親知らずの抜歯は、処置そのものも大切ですが、抜歯後も重要になってきます。これは、歯を抜いた後の処置が治りのスピードや痛みの程度が大きくかかわってくるためです。
特に、横向きに生えていた親知らずの抜歯は、歯ぐきの切開や骨の削合を伴うことが多く、通常の抜歯よりも回復に時間がかかる傾向にあります。
ここでは、抜歯後の適切なケアや注意点について解説します。
術後24時間は出血と腫れに注意する
抜歯直後はガーゼでしっかりと止血を行いますが、少量の出血が数時間続くこともあります。また、抜歯から1~2日後にかけて腫れが目立ってくることもあります。冷たいタオルや保冷剤で患部を軽く冷やすと腫れを抑えるのに効果的です。
ただし、過度な冷却はかえって逆効果になることがあるため、注意が必要です。
食事は柔らかいものを選ぶ
術後数日は、患部を刺激しないように食事内容にも気を配る必要があります。うどんやおかゆ、スープなどの柔らかくて温かすぎないものを食べるようにしましょう。硬い食べ物や刺激物、アルコールなどは出血や痛みを悪化させる可能性があるため、術後は避けるべきです。
また、抜歯した側では極力噛まないよう意識することも大切です。
うがいや歯磨きは慎重に行う
抜歯直後は強いうがいを避け、歯磨きも傷口を避けてやさしく行うことが推奨されます。強いうがいをすると、血のかさぶた(血餅)が取れ、ドライソケットと呼ばれる激しい痛みを伴う状態になることがあります。歯科医師の指示に従って、丁寧な口腔ケアを心がけましょう。
処方された薬は指示通りに服用する
術後に処方される痛み止めや抗生物質は、症状がなくても決められた通りに服用することが大切です。自己判断で服用を中断すると、感染や痛みの再発につながる可能性があります。特に、感染を予防するためには、抗生物質を飲みきることが大切です。
指示された時間や用法・用量を守って服用しましょう。
異常がある場合はすぐに歯科医師へ相談する
抜歯後に発熱、強い腫れ、膿のようなものが出る、激しい痛みが続くといった異常が見られた場合は、早めに歯科医院を受診することが大切です。早期に発見し、対応することによって、重症化を防げます。
不安な症状がある場合は、自己判断せず遠慮なく相談しましょう。
まとめ

親知らずが横向きに生えることは決して珍しくありませんが、放置していると隣の歯を圧迫したり虫歯や歯周病のリスクを高めたりします。さらには、顎の痛みや神経への影響といった深刻なリスクへとつながる恐れもあります。
横向きに生えた親知らずの抜歯は、一般的な抜歯と比べて難易度が高く、術後の腫れや痛みも出やすいです。そのため、信頼できる歯科医師のもとで十分な説明を受けた上で処置を行うことが望ましいです。
親知らずに違和感を覚えたら、我慢せず早めに歯科医院を受診しましょう。自分の親知らずの状態を知り、正しい対処を取ることが、健康な口元を保つ第一歩になるのです。
親知らずの状態が気になる方は、仙台市宮城野区「福田町駅」より徒歩4分にある歯医者「色川歯科医院」にお気軽にご相談ください。
当院では、虫歯・根管治療や予防歯科、小児歯科、マウスピース矯正、インプラントなど、さまざまな診療を行っています。診療メニューはこちら、WEB予約・LINE予約も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。