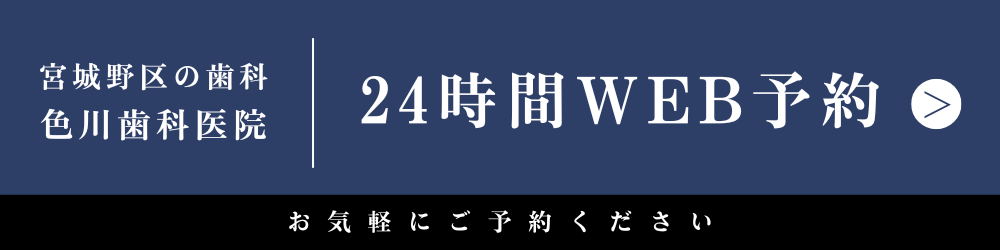2024/07/16 ブログ
扁平苔癬(へんぺいたいせん)をご存じですか?
目次
扁平苔癬とは
皮膚や口腔粘膜などに生じる難治性の炎症性疾患です。
特に口腔内に出来たものを「口腔扁平苔癬」と呼び、この口腔扁平苔癬のなかの約1%が癌化すると言われている角化異常を伴う慢性炎症性粘膜疾患です。

症状
Ⅰ:皮膚
皮膚に生じる場合、かゆみを伴うことが多く、紫紅色の発疹を認めます。発疹のほか水疱(水ぶくれ)や鱗状になり剥がれ落ちること(鱗屑)もあります。
好発部位は胴体のほか、手首や手の甲・脚などに発症します。
Ⅱ:口腔粘膜
見た目は白いレースがかかったような網目状の模様の粘膜になります。白いレース模様のなかに赤く炎症を生じた潰瘍やびらんを伴うことが多くあります。
両側に発症することが多く、その好発部位は頬粘膜が約80%と多いですが、そのほか歯肉・口蓋粘膜(上顎)・舌などにも発症します。
40~60代の中高年の女性に多く見られるという特徴もあります。
自覚症状
自覚症状が無く経過することもありますが、次のような自覚症状が現れる場合も少なくありません。
・飲食物や歯磨きなどの刺激などによる痛み
・刺激物を食べた刺激によるしみ
・口内炎
・舌の痛み
・味覚異常
・灼熱感やピリピリ感
・口を開けた時に違和感や突っ張る感じがする
扁平苔癬は感染症ではないのでヒトからヒトに感染する疾患ではありません。
皮膚における扁平苔癬は1~2年ほどで治癒すると言われていますが、口腔扁平苔癬は長引く傾向にあり、なかでも約20%が再発すると言われています。自覚症状がない場合は経過観察をすることが多く、自然治癒の割合は2~3%程度とされていますが、これは何らかのきっかけで誘発因子が消失したことによるものと考えられています。口腔扁平苔癬が癌化するメカニズムははっきり分かっていません。癌化するか否かは判別が難しいため注意深く経過観察する必要があります。

原因と治療方法
原因がさまざまであること、メカニズムが解明されていないことなどから治療方法が確立しているわけではありません。
一般的には副腎皮質ステロイド軟膏・うがい薬の処方をしつつ、症状の確認と経過観察を行いながら、それぞれの症状や原因に対する対処療法がおこなわれます。
Ⅰ:自己免疫疾患
詳しく解明されたわけではありませんが、皮膚や粘膜にある抗原に対し免疫機能が反応していると考えられています。白血球が口腔内の皮膚細胞を攻撃してしまう自己免疫疾患が示唆されています。
Ⅱ:金属アレルギー
金属アレルギーが疑われる場合は皮膚科で歯科金属に関するアレルギー検査を行います。歯科金属にアレルギーがある場合は、原因となっているすべての金属の詰め物や被せ物、義歯を除去し、金属を含まない材料(セラミック・ノンクラスプデンチャーetc.)での治療をおこないます。特に現在は使われていませんが、昔の歯科治療で使用されていたアマルガム合金は、歯
科金属の中でも発症率が高い傾向にあることが分かっています。そのため古い金属は除去する必要があるのです。口の中の金属同士が触れ合うことで金属イオンが溶け出す際に生じるピリッとした痛み(ガルバニー電流)も間接的な原因とされています。
Ⅲ:薬物アレルギー
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)・経口血糖降下薬・利尿薬・β遮断薬(血圧の薬)などで報告があります。
Ⅳ:C型肝炎ウィルス
過去の統計からC型肝炎ウィルス感染者の多くが口腔扁平苔癬を発症していることが報告され、何らかの関連があると言われています。ですが今のところはっきりしたメカニズムや関係性は解明されていません。
Ⅴ:ストレス・喫煙
ストレスや喫煙は口腔内環境を低下させるだけでなく、本来の免疫力を低下させることから、口腔扁平苔癬をさらに悪化させる要因となっています。
扁平苔癬の際の口腔ケア
口腔内は清潔を保つことが大切です。出来るだけ患部を刺激することも避けましょう。刺激を最小限にするためヘッドが小さく、やわらかい毛質の歯ブラシを使います。歯磨剤は出来るだけ低刺激性のものを選びましょう。