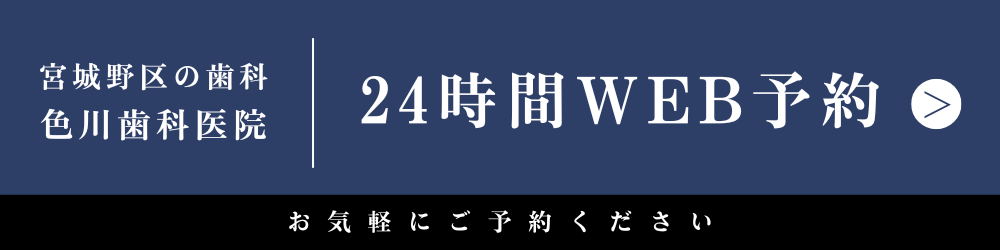2024/05/01 ブログ
全身疾患をお持ちの方の歯科治療について
年齢を重ねるにつれ、多くの方が全身疾患を持つようになります。
歯科治療において局所麻酔の使用や、出血を伴う外科処置、抗生物質の処方などを行ううえで全身疾患を把握するということは、薬剤の種類や歯科処置の内容に関わる大切な情報です。
今回は代表的な全身疾患と歯科治療における注意点について詳しく見ていきましょう。

主な全身疾患
Ⅰ糖尿病
糖尿病の合併症のひとつに歯周病があります。
歯周病に罹患すると、その歯周病菌が炎症を起こした歯肉から体内に侵入します。
通常、免疫機能により細菌自身は働きを失いますが、これら細菌の死骸が持つ毒素は炎症物質(サイトカイン)を増産させます。この炎症物質(サイトカイン)は、血糖値を下げるホルモン「インスリン」を攻撃するため、血糖値が下がらなくなり、常に血糖値が上昇した状態、つまり血液中が糖だらけになってしまうのです。糖で充満した血液は活性酸素を作り、この活性酸素が体内の血管を次々に壊してしまうのです。これが糖尿病と歯周病の関係です。このサイクルがどんどん進むと血糖値の制御が効かなくなり糖尿病と歯周病の両者
を憎悪させてしまうのです。
糖尿病に罹患すると、免疫機能が脆弱になるため感染症に罹りやすくなります。また血流の悪化から傷の治りが遅かったり悪かったりしますので、抜歯などの外科的処置においての感染症には十分に注意する必要があります。過度のストレスで血糖値が変化しやすく昏睡状態を招く恐れもありますので空腹時の歯科受診はなるべく控えましょう。
Ⅱ高血圧
高血圧の方は血圧をコントロールするため降圧剤を服用されています。
高血圧の方は歯科の使用薬剤や歯科処置に対する緊張やストレスで急激な血圧変化をおこしやすくなります。
一般的に降圧剤は朝に服用することが多いため、血圧が正常範囲のコントロール下にある午前中に歯科処置をすることが望ましいでしょう。血圧は日によって大きく変化しやすいものですので、体調が優れない場合、血圧変動が普段と異なる場合は歯科治療をお休みして医師に相談していただくこともあります。
Ⅲ骨粗鬆症
骨粗鬆症によりビスホスホネート製剤(BP製剤)を服用している場合、副作用として抜歯後の顎骨壊死の可能性が挙げられます。定期的に注射をしている方も同様の可能性があります。ビスホスホネート製剤は服用すると長く体内に残りますので、直前に休薬しても意味はなく一定期間の休薬が必要とされています。休薬により全身へのリスクが重大になる場合もあるので自己判断での休薬はせず、担当医と連携し休薬の有無を判断する必要があります。
最近では休薬する必要性がない場合あることが報告されたり、休薬せずとも歯科治療が行える薬剤が誕生したりもしています。
担当医師に相談し、休薬の有無を確認しながら進めていくことが望ましいでしょう。
Ⅳ狭心症・心筋梗塞・脳梗塞
心筋梗塞は、動脈硬化により血液循環がうまくいかなくなる病気です。
この動脈硬化は、生活習慣の乱れ・過度のストレスにより引き起こされることが知られていますが、近年では歯周病などの細菌感染も要因の一つであることが分かってきました。
細菌が血管内に入り込むと動脈硬化を引き起こす塊(血栓)が作られ、血流に乗って流された際、心筋付近で詰まることを心筋梗塞・脳で詰まることを脳梗塞と言います。
この既往があると、血液が詰まらないよう血液をサラサラにする薬が処方されています。
この場合、抜歯などの観血処置では血が止まりにくくなる可能性があります。また発症から半年はリスクが高いため歯科治療は最小限に抑えることが望ましいでしょう。

このように全身疾患を把握することは、歯科治療を安全にスムーズに進めるうえで知っておくべき重大な情報と言えます。
ですので問診表は出来るだけ正確に記載をお願いします。お薬手帳お持ちいただくことが望ましいでしょう。
歯科治療を受けるにあたり自己判断による内服薬の中断も避けてください。
また、現在通院中の場合も全身状態の変化や服用薬の量や種類などの変更があった場合はお申し出いただくようお願いいたします。